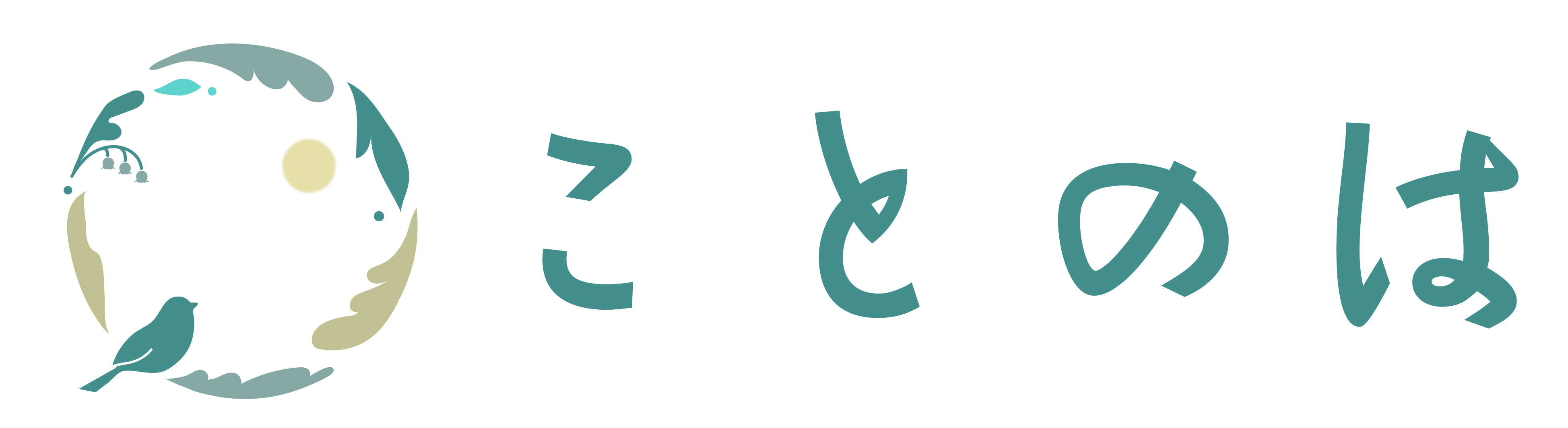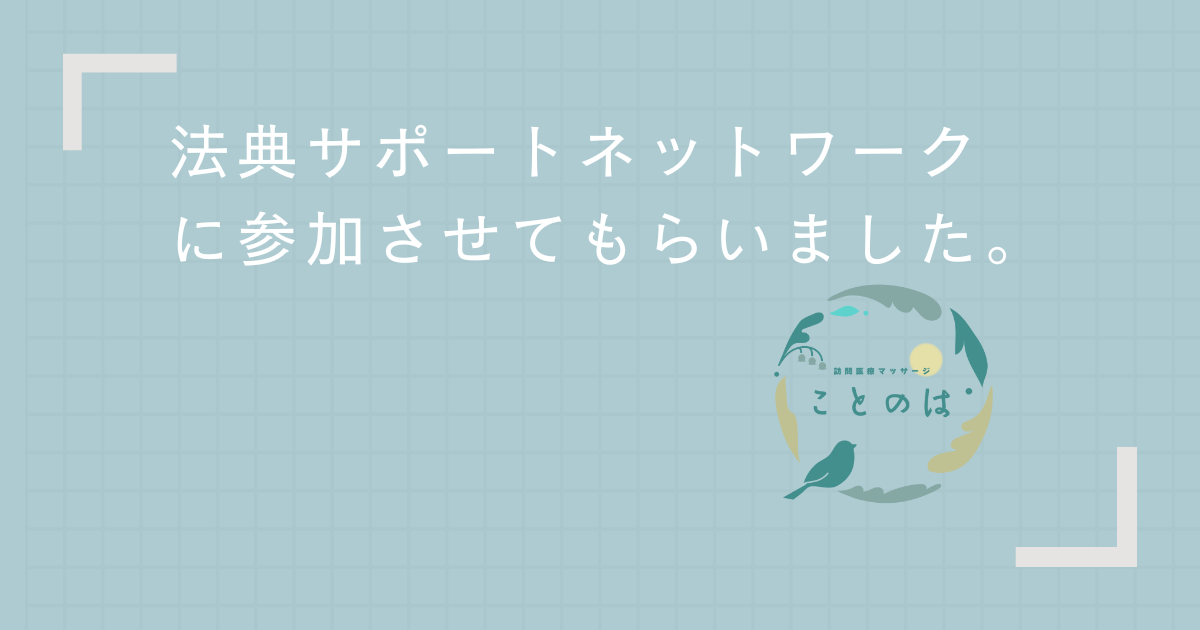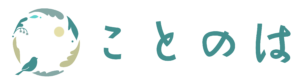はじめに
先日、船橋市で開催された防災セミナーに参加させてもらいました。
正直な所、一人での参加は何となく緊張してしまいましたが、地域の職種間を超えた交流をさせていただき、また市役所の方や地域の防災委員の方の話には災害時の新たな視点となり勉強となりました。
船橋市の防災対策、避難所の実情、在宅避難の支援の課題、さらには地域支援ネットワークの構築について個人的な私見も交えながらまとめてみます
そしてせっかくなので多く方が気になるであろう「避難所のトイレのこと」について質問させてもらいました。
すごく簡単にまとめるとこのような感じだったと思います↓

・以前の大規模災害の際はトイレの衛生状況について問題となったのは確かだが、その後は避難所の改善について国も推進している
・船橋市も含め、携帯トイレセットを一回一回交換してもらえるよう想定より多く準備している(企業との連携も進みプッシュ式の支援となる)
・問題としては、避難されている人はトイレを控える傾向があり、水分不足などもあり健康状況が危惧されている
セミナー内容の概要
■ 船橋市役所の職員の方による講話
市役所の防災担当者は、船橋市の地盤状況や近年の地震被害の実態について説明してくださいました。特に、石川県での震災支援に派遣された写真を交えた経験談は印象的で、避難所運営や物資供給の課題、そして事前の備えの重要性が強調されていました。
■ 防災委員会(防災士)の講話
続いて、地域の防災士の方による講話では、「自助・共助・公助」に加え、地域内での「近所」の支え合いの大切さが語られました。
行政だけではなく、住民同士が顔を合わせ、コロナ以降あまり行われなくなった避難訓練など、地域の中学生なども巻き込んでいくことで災害時の迅速な対応が可能になるのではないかと指摘されました。
また、地域の道路事情も実際の災害時には障害となる事を問題視しているようで、高齢者や障がい者など移動が困難な方々への支援体制の強化も求められていました。
【避難所のトイレ事情と健康リスク】
従来、避難所のトイレは衛生面で問題が指摘されることが多かったものの、現在は使い捨ての携帯トイレセットが導入され、不衛生な状況は改善されてきているようです。
しかし、新たな課題として、被災者が水分摂取を控える傾向があり、その結果、トイレの使用回数が減少し、健康リスクが懸念されています。船橋市では避難所のトイレセットの備蓄が十分に整えられているというお話でしたが、今後は水分補給の啓発や健康管理の取り組みをさらに強化する必要があります。



インターネットの情報だけでは、「トイレの不衛生さ」を煽るような話も多くありますが、市役所の方の直接の話は勉強になりました。ただ、まずは自分でも備えておくことが重要ですね。
【在宅避難の必要性と支援の課題】
避難所への移動が困難な方、特に病気や身体の障害を持つ方々にとって、在宅避難は必須の対策です。しかし、在宅避難を実施する家庭では、十分な備蓄や医療支援の確保が困難な場合も多いのが現状です。
加えて、行政や地域の支援ネットワークを活用し、在宅避難者向けの備蓄支援、近隣住民との連携による見守り体制の整備、在宅避難時の注意点や支援制度の案内など、総合的な対策が求められています。
本当の意味での災害時における在宅避難時の最低限の準備品として、私は「一週間分の飲料水」と「一週間分の使い捨てトイレセット」あたりを準備するだけでも違うのではないかと考えましたがどうでしょう?
※あくまでも「必要最低限の場合」です
【地域支援ネットワークの構築】
法典地区やその近郊では、民生委員、自治会、医療・福祉関係者が定期的な勉強会や意見交換会を通じて、顔の見える関係を築いてくことを目的としてこうしたネットワークが少しづつ形成されているようです。こうした取り組みにより、地域内での情報共有がスムーズになり、災害時だけでなく日常生活の中で困難を抱える住民へのサポート体制が整いつつあるのかもしれません。
もちろん机上論だけでは災害時の実際の運用は難しいことも多いでしょうが、多方面の専門家が連携することで、災害発生時の迅速な対応はもちろん、平常時からの防災意識や地域全体の安心・安全の基盤が強化されていくと感じました。
【まとめ】
今回のセミナー参加を通じ、船橋市の防災対策には一定の安心感がある一方で、特に在宅避難者への支援や、地域支援ネットワークのさらなる強化が今後の大きな課題であることが明らかになりました。防災は行政の取り組みだけでなく、住民一人ひとりが意識し協力することで成り立つものです。私自身も、これから地域の防災活動に積極的に関わり、現場で感じた課題や改善策をなどを訪問時等にも話をさせてもらいたいと思います。
今回の開催にあたり、準備や運営をされた関係者の皆様、参加させて頂きありがとうございました。